ウェブ・ジャーナル「Seismopolite」がアーティスト・イン・レジデンスを特集
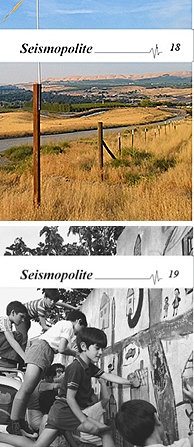
Seismopoliteウェブサイトより
Seismopoliteは「アートと政治のジャーナル」をキャッチコピーに、興味深いテーマ設定で世界のライターから記事を集め、年に3号くらいのペースでノルウェーのオスロから発信されているウェブ・マガジン。その最新の2号は、世界的に急増している「アーティスト・イン・レジデンス(AIR)」の近年の展開を、理論と事例の両面で特集している。
AIRはもともと、アーティストに日常生活の拘束から解放された時間と場所を与え、彼らの作品制作を支援することを目的に行われるのが一般的で、レジデンシーはいわば、誰にもじゃまされない「隠れ家(retreat)」であり、新しい創造の「インキュベーター」だった。しかしここ20年ほどは、アートの「ソーシャル・ターン」(クレア・ビショップ)、「コラボレイティブ・ターン」(マリア・リンド)に歩調を合わせるように、AIRも、アーティスト個人の作品制作より、コミュニティとの協働から生まれるソーシャル・プラクティスを意識したものが多くなっているという。この特集の記事の多くも、後者のタイプの“ソーシャリー・エンゲイジド・レジデンシー”に注目している。
AIRの文脈をたどり、今日の“社会形態”としてのAIRを論じた「アーティスト・レジデンシーの社会生活:見知らぬ土地と人々との交流」(Marnie Badham)、カナダ、エドモントン市役所での1年にわたるレジデンシーを事例に、AIRのどのような面を重視し、評価するかを論じた「埋め込まれた美学:論争と社会革新の場としてのアーティスト・イン・レジデンス」(Dr. Michael Lithgow and Dr. Karen Wall)、AIRの労働経済を論じる「アート・イン・レジデンシー:先行き不安、それとも好機?」(Sebastjan Leban)は、日本のAIRやアートプロジェクトを考える上でも参考になりそうだ。
その他、パキスタン、ブラジル、エクアドルのキトでの事例、米国ヴァージニア州の自宅にAIRを開設したアーティストとワシントン州立大学の研究者対象レジデンシーのディレクターが「ルーラルAIR」をテーマに語る対談などが掲載されている。
(秋葉美知子)



最近のコメント