Culture Strike: Art and Museums in an Age of Protest
ローラ・ライコヴィッチ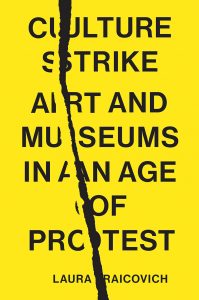 は、、アクティビスト・キュレーター、批評家、ソーシャリー・エンゲイジド・アートの唱道者として知られ、2018.2.26のブログで紹介したように、ニューヨークのクイーンズ美術館の館長を務める中で、理事会との考え方の相違がもとで辞職した経験を持つ。近年、米国の美術館が、(差別問題をはらむ)展示内容、(倫理的に問題のある)大口スポンサーとの関係、スタッフの(不公平な)雇用などをめぐって、論争や抗議行動の舞台となることが増えている。ライコヴィッチは本書で、この状況の背景を考察し、美術館というインスティチューションのあり方について、彼女の苦い経験に基づく問題提起と、今後の希望的方向性を率直に述べている。その論旨は、Robert R. Janes, Richard Sandell(編)による『Museum Activism』や、2019年のICOM(国際博物館会議)で提案されたが採択はされなかった新しいミュージアムの定義に通じる。つまり、ミュージアムは「過去の遺産の取得、保存、調査、伝達、展示」にとどまらず、「現在の紛争や課題を認識し、それらに取り組みつつ、社会の委託のもと、人工品や[動植物・鉱物などの]標本を保管し、将来の世代のために多様な記憶を守るとともに、すべての人々に遺産に対する平等な権利と平等なアクセスを保証する」「民主的、包摂的かつ多声的な空間」でなければならないという考え方だ。そこでのミュージアムは、自らの価値観をはっきりと示す必要がある。「ミュージアムの中立性は神話だ」と、ライコヴィッチも本書で繰り返している。美術館は常に中立性を主張するが、それは、(西洋の)白人至上主義、資本主義、ヘテロ家父長制の価値観に基づく権力構造を覆い隠している。Unlearnig, Undoing、Remaking(これまでの知識・習慣を忘れ、無効にし、作り変えること)によって、多様で、平等で、包摂的な文化空間を生み出そうと本書は促す。もちろん、米国の歴史・文化を理解することが前提だが、問題となった事例の数々は、日本の私たちも他山の石として読みたい。
は、、アクティビスト・キュレーター、批評家、ソーシャリー・エンゲイジド・アートの唱道者として知られ、2018.2.26のブログで紹介したように、ニューヨークのクイーンズ美術館の館長を務める中で、理事会との考え方の相違がもとで辞職した経験を持つ。近年、米国の美術館が、(差別問題をはらむ)展示内容、(倫理的に問題のある)大口スポンサーとの関係、スタッフの(不公平な)雇用などをめぐって、論争や抗議行動の舞台となることが増えている。ライコヴィッチは本書で、この状況の背景を考察し、美術館というインスティチューションのあり方について、彼女の苦い経験に基づく問題提起と、今後の希望的方向性を率直に述べている。その論旨は、Robert R. Janes, Richard Sandell(編)による『Museum Activism』や、2019年のICOM(国際博物館会議)で提案されたが採択はされなかった新しいミュージアムの定義に通じる。つまり、ミュージアムは「過去の遺産の取得、保存、調査、伝達、展示」にとどまらず、「現在の紛争や課題を認識し、それらに取り組みつつ、社会の委託のもと、人工品や[動植物・鉱物などの]標本を保管し、将来の世代のために多様な記憶を守るとともに、すべての人々に遺産に対する平等な権利と平等なアクセスを保証する」「民主的、包摂的かつ多声的な空間」でなければならないという考え方だ。そこでのミュージアムは、自らの価値観をはっきりと示す必要がある。「ミュージアムの中立性は神話だ」と、ライコヴィッチも本書で繰り返している。美術館は常に中立性を主張するが、それは、(西洋の)白人至上主義、資本主義、ヘテロ家父長制の価値観に基づく権力構造を覆い隠している。Unlearnig, Undoing、Remaking(これまでの知識・習慣を忘れ、無効にし、作り変えること)によって、多様で、平等で、包摂的な文化空間を生み出そうと本書は促す。もちろん、米国の歴史・文化を理解することが前提だが、問題となった事例の数々は、日本の私たちも他山の石として読みたい。



最近のコメント